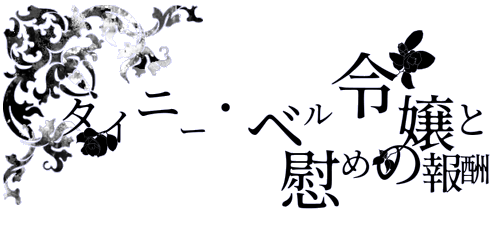イザベルは鏡の中の自分を見つめた。
肩からおろした色のぼやけた金髪。薄い紫色の瞳。隈も浮かんでいなければ吹き出物もなく顔色はとても良い。そして、すらりと両耳から伸びた長ネギ。肌よりも瑞々しく艶々としているのは、うら若き乙女として嘆くべきことなのかもしれない。
侍女のメリッサが丁寧に髪をくしけずる。幼い時分から付き合いのあるひとりだ。呪いで耳から長ネギが生えたイザベルに初めこそ目を丸くしたものの、すぐに頭を切り替えた。優秀な侍女は晩餐会の身支度を手際よく進めてくれている。
「年々美しくなっていくお嬢様の髪を結うのは私の一番誇りのあるお仕事で、どのような髪型でお嬢様をより一層可憐にお魅せするのか悩むのも一番の楽しみなのですが、こんなにも悩んだのは初めてです」
「ごめんなさい」
素直に謝罪すると鏡の向こうでメリッサの鳶色の瞳に炎が揺らめいた。
「いいえ、いいえ! お嬢様、壁があればあるほど腕が鳴るというものなのです!」
もうひとりの侍女のアンが宝石箱を片手に尋ねてくる。
「髪飾りはどうなさいますか?」
「これをお願い」
迷いなく指差したそれに、二人の侍女はとろけそうな笑みを浮かべた。
「まあ! 初めて見る素敵な飾りでございますね」
「ええ! 夢のように咲き誇るお嬢様によくお似合いです。旦那様、それとも若様からの贈り物ですか?」
贈り主も贈られた経緯もよく知っているはずなのに、とぼけた声で何度目にもなる疑問符を投げてくるのがなんともこそばゆい。
「……あのね、殿下にいただいたものなの」
もう何度目にもなる返事なのに、恥ずかしさと喜びとで唇が震えた。
「だから、とびきり綺麗に結ってくれる?」
「かしこまりました」
まだ学生の身分であるイザベルは、ヘンリー・ロー・サージェント第四王子殿下の婚約者とはいえ、デビュタントを済ませていない。王太子殿下の末子であるヘンリーが魔術師に就いて公務から離れた立場であり、イザベルには第一王子妃のように公務として『社交』に励むよう王室から特別指令が出てはいないからだ。学生の本分を存分に果たすよう――学業に励み、青春を楽しむよう――言われているくらいである。故に、学院を卒業するまで社交界でも正式にお披露目はされていない。
加えて、父親のオーキッド侯爵もその後継の兄も暇と資金さえあれば王立魔術研究所に籠もることを好む魔術師であり、オーキッド邸で業務的に開かれた茶会や夜会といったものは最低限かつ内々のものに限られた。当然、イザベルもそういった催し物には数えるほどしか参加したことがない。本日招かれた王宮の晩餐会も内々のものではあるが、貴人に会う装いで着飾る機会があまりない年頃の娘にとって、こんなにもわくわくすることはない。
「ごきげんよう、レディ・タイニー・ベル。昼間ぶりだね」
馬車まで迎えにきてくださったそのひとは、涼やかな声色で挨拶をした。流れる動作で手を取られ、外に出る。
「こんばんは」
煌めく見事な銀髪に、青色の瞳。ヘンリー・ロー・サージェント王子殿下である。昼間に会った時のくたびれたローブではなく、黒色で品の良いイブニングコートを羽織っていた。青い瞳は夕明かりに照らされている。
ヘンリーの襟元にはアメジストのタイピンが輝いている。曙の空のように、薄青と薄紅を淡く繋ぐ輝きの石。
「今夜の君は可愛いね。うん、とびっきり可愛い」
惜しみなく顔をほころばせるヘンリーに、イザベルの頬が熱くなる。
今宵、イザベル・オーキッド侯爵令嬢が身に纏ったのは白色から薄紅色へ、咲き染めの花のように淡く色づく布地のドレスである。襟と七分袖には繊細な椿の刺繍が銀の糸であしらわれていて、首元と腰元に青いリボンが巻かれている。ふわりと広がるドレスの裾にも蔓椿と葉が丁寧に縫い取られている。
「先日は、素敵な贈り物をありがとうございました」
緩やかにサイドを編まれた長い金髪は椿を象った髪飾りで品良く纏めてもらった。明かりを受けると朱鷺色の花弁が星を散らすようにきらきら輝く。
眩しげに青い瞳が細められる。
「よく似合ってる」
「ありがとうございます……」
「贈ったものを身につけてもらえるのは嬉しいけれど、なんだか照れるね」
くすぐったそうに敷いた笑みを受け、イザベルもつられて口元を緩める。すると、ヘンリーが身をかがめ、長ネギに、否、耳元に囁いてきた。
「僕の給料が今はそれを贈るので精一杯なのは内緒ということで」
「箝口令ですね」
「そこは二人だけの秘密と言ってほしいかな」
そのひとは困ったように笑って眉を下げ、腕を差し出した。イザベルがこくんと頷くのを待ってから差し伸べられた腕が王宮に優しく促す。
幼い頃から通い慣れた王宮ではあるが、夜のとばりが降り始めた回廊の美しさは何度見ても格別だ。窓から差す陽の傾きに従い、回廊は橙色に染まっていく。よく磨かれた床に浮かぶ淡い橙の光が美しい。
「やあタイニー・ベル。しばらくぶりだね」
顔を上げたその先、視線の向こうに映るのは、どこまでも眩しい金色だった。黄昏と彼の髪の色は、その輝きがよく似ていた。
その光を身に受けながら、第二王子殿下は普段と変わらぬ鷹揚さでもって笑んでみせた。
臣籍降下を果たして久しい彼の肩書きには正しくは「元第二王子殿下」と冠せられる。だが、イザベルの兄と彼は恐れ多くも友人同士で、よく家に遊びに来てくれていた。兄は今でも彼を「殿下」と呼ぶ。
イザベルにとっても優しく気さくなラグランドお兄様は、今でも「殿下」なのである。
「ラグランドお兄様、こんばんは」
淑女の礼をとったイザベルにラグランド・S・サージェント第二王子は優雅に笑みを返す。と――
驚きを含んだ視線を上からじっと注ぎ、疲れたようにかぶりを振った。
「……おかしいな。タイニー・ベルの耳にネギが生えたように見えるんだが。遠征疲れかな」
「大丈夫ですよお兄様。呪いなので見間違いではありません」
へらりとイザベルが口元に弧を描くと、ラグランドもまた弟ヘンリーと同じ色合いの瞳を眇めた。そしてそのまま弟に掴みかかった。がなり出しながら笑みを絶やさぬ姿勢、どこまでも器用なひとである。
「呪い? この愚弟! この研究馬鹿! 嫁入り前の女の子になんてことを!?」
「兄上」
ヘンリーはかぶりを振って、大仰に嘆息した。吐息とともに至極真面目な面持ちで告げる。
「年頃の女の子でなくともショッキングかつ斬新な呪いです」
「そうだけどそうじゃないよね!? ああもうこの魔術馬鹿は……」
彼は半分あきらめたような表情でぐったりと肩を落とした。
身体に害がないことを簡単に二人で説明すると、兄王子はようやくヘンリーを解放する。そして、瞬きを繰り返す。
「弟よ、お兄様の目にはお前の頭までお花畑になってしまったように見えるんですが此は如何に」
「大丈夫です兄上。魔術なので気のせいではありません」
ヘンリーがきっぱりと頷いて宣言した。煙るような淡い色の菫が一輪、ヘンリーの銀髪の上で揺れている。
「いやいやいや! そんないつになく真剣な顔で言われましても! 王都で流行ってるの? 少なくとも俺が遠征旅行に出るまでは呪いだか魔術だかで頭飾るのなんて流行ってなかったはずだけど!?」
「さすが兄上! 目の付け所がシャープですね」
「はい。さすがはラグランドお兄様です。わたしも今気づきました。ヘンリー様、綺麗な菫ですね」
「ありがとう」
ヘンリーが目許を和らげ、右の人差し指をくるりと振った。
「さあ、タイニー・ベル。ラグランド兄上には何色の花が似合うかな」
にっこりと口の両端を緩めながら、 ヘンリーは兄王子の様子をうかがう。
ラグランドは嫌そうに形の良い眉を寄せた。
「おいおいヘンリー・ロー、なにを考えている」
「兄上はいつだって僕たち二人にお優しい。そう思っていますよ」
兄王子は依然としたまま困惑しきりの視線をヘンリーに投げている。
「おとうさま!」
甘く舌足らずな声と駆け足の音が回廊に響いた。
夕日に染まった金髪をふわふわと揺らし、小さな少女が嬉しそうに息を弾ませて駆けてきた。
「リル!」
ヴァイオリンケースを足下に置き、ラグランドは腕を広げて娘を迎える。
「おかえりなさーい」
遠征旅行から帰って来たばかりの父親の胸に、少女がまろぶような勢いで飛び込んだ。
「回廊では走らないと約束したよね。リルが転んで怪我をしたらお母様がひどく心配する」
「おとうさまも?」
「もちろん。でも、心配で胸が潰れてしまったからお父様はもうだめかもしれない……。この遠征旅行が終わったらお母様に……ベルに伝えたいことがあったんだが、くっ」
娘のリルを抱き上げたまま、ラグランドが大仰によろめいてみせた。父より高い位置にある黄昏の空を煮詰めて溶かした色の瞳が不安そうに揺れる。
「……お母様に、愛していると伝えてくれ」
「おとうさまあ、しなないで」
ぎゅっと首にしがみつかれ、ラグランドの身体が大きく傾ぐ――
「はいはい。兄上、そこまでです。リルを泣かせたり落として怪我でもさせたりしたらベルマ義姉上が実家に帰りますよ」
「そうですよラグランドお兄様。いくらなんでも悪趣味です」
兄王子の背を支え、ヘンリーが呆れた口調で諫めた。イザベルもやんわりと援護をする。
「ヘンリー・ローとタイニー・ベルにはよく効いたんだけどなあ」
あの頃は可愛かった、と第四王子とその婚約者の幼少期をよく知る第二王子がなにやら呟くのが聞こえてくる。
ラグランド殿下は昔からイザベルの兄を訪ねてよくオーキッド侯爵邸に遊びに来ていたわけだが、二人で外に遊びに出かけるときなどには小さなヘンリーとイザベルを器用に撒いた。「三国一美しい王子」と謳われていた彼は、金髪碧眼の儚げな容姿を惜しみなく使い、天に召されそうなふりを何度もしてみせた。
ヘンリーとイザベルはもちろん何度も騙された。ある日、あまりにも安らかな顔で長椅子に横たわるラグランド王子を発見したときには、お別れの棺を盛大に飾って笑顔で見送ろうと屋敷中の花をかき集めたものだ。イザベルの兄が不敬罪覚悟で熟睡中のラグランドの頭を叩いて起こし、葬儀の準備を慌てて止めに入ったのは記憶にまだ新しい。
「大丈夫だよリル。君のお父様のとっておきの秘密を教えてあげよう」
今にも涙があふれそうなリルの蜂蜜色の瞳にヘンリーが笑いかけた。
「いつか君を攫いに来る王子様の顔を見るまでは死んでも死ねないって、君のお父様は演奏旅行に行くときも戻るときもお母様に誓っているんだって」
「ほんとう?」
「本当よ」
ラグランドの細君の涼しげな声が回廊の空気を震わせた。上品に結い上げた栗色の髪をやわらかになびかせてこちらに近寄ってくる。品の良い青いドレスに身を包んだベルマ夫人は、艶やかな唇の前に繊細なレースの手袋に包まれた細い人差し指を立てた。
「今日からリルも知っている、お父様のとっておきの秘密ね」
「皆が知っていたら秘密って言わない……」
第二王子が情けない声を出すと、奥方は蜂蜜色の美しい瞳を細める。
「そういえば今回お戻りの分の誓いをまだいただいていませんでしたね。さあどうぞ、ラグ様」
「リルも聞く!」
「……ヘンリー・ロー、一つ頼みがある」
ラグランドが眉間に皺を刻み、声を低くした。
「なんです?」
「父上と母上に伝えてくれ。ラグランドは妻子と恥ずかしさとよく戦い立派に散ったと……」
「兄上には」
ぱちん。
ヘンリーが軽く指を鳴らす。回廊に光が走った。光が夕明かりに溶けて消えると同時に、ラグランドの金髪と襟に黄金色の花が開いた。蜂蜜を溶かしたようにも金を煮詰めたようにも見える色だ。
「花菱草がよくお似合いではないかと愚考いたしますが、いかがですか」
「ヘンリー・ロー、お前ねえ……」
リルを抱き込んだままラグランドが抗議の声をあげたが、不発に終わった。舌足らずの可愛い歓声が胸元で湧き上がったのだ。
「おかあさまとおんなじ色! とってもきれい!」
「そうね。リルとも同じで良い色ね」
妻と娘の瞳に映り込む花を認めたのか、ラグランドは大きく息を吐いた。
「……我が弟殿は、この兄に世界で一番似合う色をよくご存じで」
そして、ヘンリーの色とよく似た青い瞳を細めてにやりと笑う。
「あとで褒美を遣わそう。そういうわけで、俺たち一家を邪魔せず二人でゆっくり広間に来なさい」
彼はヴァイオリンケースを背負い直し、リルをもう一度抱き上げた。ベルマが「またあとで」と困ったように微笑んでくれ、イザベルも会釈した。
ラグランドは妻に目で合図して歩み出そうとしたようだが、すぐにイザベルの隣に戻ってきた。
どうしましたか、とイザベルが笑いかけると、サージェント家の姫君は小さな両手で口元に筒を作った。
「あのね、ヘンリー・ローおにいさまのお花もタイピンもタイニー・ベルおねえさまのおめめの色とおそろいね」
返事をするより先に、三度大きく瞬いた。
「みんなが知ってるひみつ。とってもすてきね」
長ネギを通って耳に届いたのは、小さな発見を誇らしげに囁く少女の声。
またあとでね、と手を振ると少女は父の肩に身を寄せて今度こそ回廊の向こうに遠ざかった。
「さすが我らが姪は、この叔父に一番似合うとっておきの素敵な色をよくご存じだ」
心臓がとくん、と跳ねた。
「やっぱりイザベルの瞳はとてもよい色をしているね」
不意に呼ばれた名前に、息を呑んだ。
声は咄嗟には出なくて、答えの代わりにヘンリーを見つめ返す。そして、真っ直ぐにイザベルを捉える青の瞳の深さに呑まれ、返事をするタイミングを失う。彼は骨張った長い指でタイピン、それから頭上の菫を撫でた。いつもどおりのヘンリーの穏和な微笑みは、静かにイザベルの胸を焦がした。
晩餐会はいつも通り、否、いつも以上に和やかに賑やかに幕を下ろした。
リルが魔術師の叔父ヘンリー第四王子に可愛いおねだりをして場を沸かせたのだ。小さなレディに手を引かれ、魔術師が国王に王妃、王太子夫妻、第一王子一家、第二王子の奥方、第三王子の頭と胸元に次々と花を咲かせる様子はなんとも不思議な光景であった。けれども、王室の誰もが目に入れても痛くないほどに可愛がっている小さなお姫様が、厳かな儀式の如く大人たちに似合う花を授けようとするさまはとても愛らしく、誰もが頬を緩めた。
その父親のラグランドも遠征旅行の疲れを見せずに上機嫌でヴァイオリンを奏でてみせ、ヘンリーとイザベルの二人にワルツを披露させた。学院卒業後のイザベルのデビュタントまでにどこまで練習が進んでいるかの抜き打ちテストである。王妃と王太子妃による直々のロイヤル指導にも王室メンバー勢ぞろいのギャラリーにも二人は縮み上がった。けれども、ステップよりも所作よりも、指導の声を飛ばすロイヤルな教官二人に真っ直ぐと目線を返すことの方が至難の業だった。――お二人とも頭に大きな花を咲かせていたので。
舌鼓を打った今夜の料理の素晴らしさ――すりつぶしたコーンにバターと鶏ガラで丁寧に煮込まれたスープと、絹のように滑らかな舌触りで甘くやさしくとろけるアイスクリームは特に絶品だった――をヘンリーと語り合っていたら、庭園の噴水にたどり着いた。ここから王城の門まで目と鼻の先である。
馬車まで送ってくださる第四王子にイザベルは向き直った。
「ロー様、ありがとうございました」
満天の星空と蒼い月に照らされたそのひとの微笑みはやはり美しかった。
「お礼は僕から料理長にも伝えておこう。おばあさまも母上も君がアイスクリームをあまりにもおいしそうに食べるものだから、君が来るときには用意しておくって言っていたよ。またいつでもおいで」
ほろほろと落ちる月明かりに照らされたヘンリーの笑みは、昼間に見るそれと変わらない穏やかさなのに、とても綺麗でなんだか落ち着かない気持ちになる。月光を浴び、庭師が丹精を込めて手入れしているであろう花々も噴水も昼間とは異なる輝きを見せているからかもしれないとイザベルはどきどきする胸を落ち着かせるように息をついた。
「はい。あの、ロー様」
「うん」
言葉に詰まるイザベルを、笑みを敷いたままヘンリーは見守っている。
いつも。いつだって、この年上の婚約者は焦らなくて良い、と言ってくれる。
深く息を吸ってから、ゆっくりと吐き出す。
「……今夜は、わたしの呪いを気にせず過ごせるようにご配慮いただきありがとうございました」
「君が気にせず楽しめたのならば何よりだ。髪飾りを贈った時からずっと楽しみにしていたものね」
案ずるような眼差しと、向けられる微笑の優しさに目が潤みそうになる。いつだってこのひとはイザベルを甘やかすのが上手だ。
銀の髪が風に揺れてなびいて、月の光に透けた。こちらを覗き込むような形になったヘンリーとの距離は自然と近くなっていて、その深い青の瞳から目を反らせなくなる。
「タイニー・ベル。やっぱり僕は君を家に帰したくない」
繋いでいた手をヘンリーに引かれ、その腕の中にイザベルの身体が閉じ込められ……そうになった瞬間、やんごとなく陽気な声が飛び込んできた。
「おお、弟よ! ヘンリー・ローよ、お前は知っていたか? 知っているよな! 優秀な我が弟ならば当然知っていたはずだ」
第二王子殿下が朗らかに噴水の向こう側から寄ってくる。ヴァイオリン奏者故か、やけに美しいメロディーの鼻歌が夜の庭園を彩った。足取りはなんだかふわふわしている。
「兄上」
「早くお前のタイニー・ベルを助けてやりなさい。お姫様にかけられた呪いは王子様の口付けで解けると相場が決まって――」
「……兄上、酔っていますね」
「酔ってない酔ってない」
「酔った者は皆そのように言うそうですが」
弟王子の冷静な指摘に第二王子殿下は「頭に花咲かせて言われてもなあ」と声を上げて笑い出した。それから弟王子と婚約者の顔――ヘンリーとその腕に閉じ込められかけたイザベル――を見比べ、瞠目するや否や顔を赤くした。青色の瞳を伏せ、彼は大きく咳払いをする。
「……すまん。お兄様は退場するので可及的速やかに続きをどうぞ」
良い夜を、と優雅に礼を取るなりラグランド王子は噴水の向こうへと姿を消した。
「ラグランドお兄様も」
やや遅れをとったイザベルの返事も届いてはいるようだ。ふわふわと歩く第二王子殿下は右手を軽く振ってくれた。
そのまま遠ざかる鼻歌に耳を澄ませていると、髪を一筋掬われた。
「レディ、続きをしても?」
ヘンリーは軽く掬い上げた金髪を、彫刻像のように美しく作られた唇の近くまで引き寄せてみせた。イザベルは続きとは何のことだろうと首を傾げ、……息を止めた。
そのひとの長い指がすっとイザベルの頬を伝い、頤を軽く押し上げた。星明かりを受けた青い瞳は甘く煌めいている。心臓は早鐘を打ち、指先に触れられた部分がじわじわと熱を帯びる。やわらかい影がゆっくりと降りてくる予感にイザベルはそっと目を閉じた。